枯れない無花果〜閉ざしてしまった篭
蓮 (ren)
『枯れない無花果(いちじく)~閉ざしてしまった篭』。
『手紙的小説』と言えばいいのか?この作品に出逢った時に衝撃が走りました。
荒削りの作品ではありますが、著者の『泥』や『毒』が文字一つ一つの『言の葉』に詰まっています。
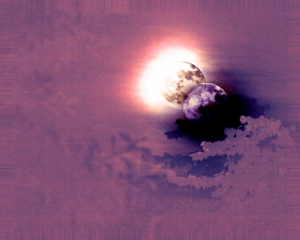
【慙愧(ザンキ)】
第 10回

会社への借金の返済の為、葵は残業を増やした。
同じ職場の友人の子、蓮と同級の哲を、迎えに行き、
ふたりを連れて織屋に戻った。
織屋工場と主屋は、たたき廊下を隔てて隣接し、
主屋の部屋で、ふたりを待たせ残業した。
廊下を入ってすぐの部屋は、主屋のお兄さんの部屋でした。
陽が暮れる少し前に、お兄さんは学生服で帰ってきて、
蛍光灯のスイッチに手が届かない私たちの為に、
先ず電気をつけ、着替えるとすぐに、
いつもふたりを遊んでくれました。
本を読んでくれたり、トランプや、ゲームをして遊びました。
工場の厚い木のドアと部屋の襖を閉めてしまえば、
機械の大きな音は、かなり遮断されます。
その日は、窓から夕暮れの光が、まだ薄く入っていて、
帰って来たお兄さんは、部屋の電気をつけませんでした。
制服の上着を脱いで、ゴロンと寝ころがって、
ふたりが遊んでいるのをしばらく眺めていました。
座る私の背後から、両腕を掴んで、私を立たせました。
お兄さんの方を見ると、窓を背にしていて、よく顔が見えません。
お兄さんは2・3回私の頭を撫でて、背中や腕を撫でました。
人に触れられる事に慣れていなかった私は、身をよじって避けると、
「遊ぼ」
お兄さんは、いつもの明るい声でそう言って、
ふたりに、スモックを脱ぐように言いました。
哲君を見ると、勢いよくスモックを脱いでシャツもとってしまいました。
お兄さんの手が、私の服にかかると、
するりと容易くスモックとシャツをとって、
ズボンと下着にも手をかけました。
困った気持ちがして嫌がると、お兄さんは先に哲君のズボンと下着をとって、
同じだからと私を安心させました。
もう一度、私の頭を撫でると、靴下だけを残して私の服を全てとり、
それを丁寧にたたんで、そばに置きました。
そして、哲君を仰向けに寝かせ、目を閉じているように言いました。
落ち着かないのか、そわそわする哲君の顔の上に、
お兄さんはシャツをかぶせ、何かを言っていました。
何の遊びが始まっているのか、分からないまま、
私は、ただ立っていました。
お兄さんの手が肌の隅々に触れ、
足の付け根に着くと、しばらくそこに留まり、手を離しました。
お兄さんは立ち上がり、制服のズボンを脱ぐと、
またゴロンと横になって肘枕をし、立っている私を眺め、
時々触れながら、機械仕掛けの人形のように、呼吸と手の動きを合わせていました。
薄暗い夕闇の始まりと、遠くで工場の機械のまわる音だけが、
部屋の中に存在する様な静けさ。
ハンティングする生き物が、あえて存在を隠す時の様に、
気配の消された、張りつめた空気。
まるで、ここには何も存在しない様な。
動くことさえも許されない程に、止まっている空気。
突然、襖が大きな音を立てて開き、
大人達が声を荒げて入って来ました。
間もなく母たちも、騒ぎに気づき、駆け寄ると急いで下着を着せました。
電気がつき、私は眩しさで目をつむりました。
誰かが、お兄さんをつかみ、怒鳴り、頭に拳を打ち下ろしていました。
お兄さんは苦悶し蹲踞り、
私を見て、指さし、
「こいつが!こいつが!こいつが」
そう何度も悲壮な弱い声を洩らしました。
気配が消されていた部屋の中は、
一転して幾つもの存在が現れ、幾つもの感情や言葉が飛び交いました。
母に連れられ部屋をでようとすると、足の裏に何かが付きました。
畳の上は水をこぼしたように濡れていて、靴下を滑らせました。
私は黙ったまま、濡れた畳を気にしていました。
今この部屋にある、ただならぬ空気よりも、
濡れた靴下のまま、靴をはく苦痛に気をとられていました。
母に左手を強く掴まれ、引っ張られるように織屋を出ました。
母の手は、私の手を強く握り、
足が縺れるほどに速く歩き、
帰り道、何度も転びそうになりながら、
母について歩きました。
車が通る大通りまで出ると、
外灯やヘッドライトの明りが、母の顔を照らしました。
ヘッドライトが当たる度、母の頬には、滴が光り、
私は、母から目を離せなくなりました。
真っ直ぐ前だけを見て、
ありったけの理性で感情を抑え、
頑なに閉じられた、母の口もと。
強く握られた手から、
得体の知れない感情が流れ込んでくるのが解りました。
突然、
「くやしい!くやしい!」
絞り出すように母から出てきた言葉は、
私に突き刺さりました。
繰り返される叫び声が、
強く握られた手から流れ込む、激しい感情が、
『罰』のように、私を打ちのめしました。
そして、お兄さんの言葉と、指したゆび先が、
更に私を責め、
この哀しみの根元は私だと悟りました。
あの部屋での出来事が浮かび、
初めて本能的な恐怖を感じました。
存在の消された、止まった空気の、
あの部屋では全く恐怖心など無かったはずなのに。
眠れない夜の暗闇以上に、
身動きできない程に 在った存在の恐怖。
『罰』が哀しく私の全身に響いて、もう歩くことも出来なくなっていました。
母を、こんな姿にしているのは、私。
幼かった私の中には、ただ、『私は悪い子』として膨らみました。
握られた左手は肩から痛み、
握りかえす力もありませんでした。
手が離れてしまえば、
母は、このまま私を見ずに、置いて行くに違いない。
もう二度と母から手を掴んではくれない。
母の手が、このまま力を失わないことを願いながら、
この手の痛みが消えないことを願いながら、
一心に母に添って歩きました。

 前のページ へ
前のページ へ