枯れない無花果〜閉ざしてしまった篭
蓮 (ren)
『枯れない無花果(いちじく)~閉ざしてしまった篭』。
『手紙的小説』と言えばいいのか?この作品に出逢った時に衝撃が走りました。
荒削りの作品ではありますが、著者の『泥』や『毒』が文字一つ一つの『言の葉』に詰まっています。
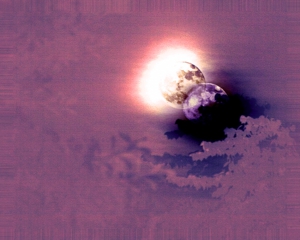
誤 織
第 2回

【誤織】
葵が嫁いだのは、大きな墓地の隅を、塀で区切っただけの木造の平長屋だった。
薄い長板を貼っただけの外壁は、湿気で剥がれ波打っていた。
窓のガラスは割れ、ベニヤ板で外からふさいであった。
玄関が南向きにあるわりには、中は暗く、陽が差し込まない。
土間に小さな台所が見えた。水道がある。
表に共同の井戸が設置してあったので、水道があるのには驚いた。
葵が台所に立つと、
「水は、外の井戸を使うから。」
そう言って、蛇口に置いていた葵の手の上に、夫の妹が自分の手を置いた。
家の前にある、町内の共同井戸が台所のようだ。
六畳と二畳、四畳半、この長屋で、そこに姑と、姑の内縁の夫、
葵より四歳年下の夫、雄一、
そして夫の下に二歳ちがいで続く四人の妹との、八人が暮らすことになる。
ごちゃごちゃと、常に神経をすり減らしていた実家から出たい一心で、結婚という道を選んだはずなのに。
ため息をつきながら、もう一方で、さてどこから修理にかかろうか、という意欲感も沸き起こっている自分に苦笑いした。
実家も相当粗末な建て方をした古い借家だったが、
葵の父は、H電車を定年退職したあと、手先の器用さもあって、
大工の臨時職人をしていた。
休みの度に家の中を修繕し、建て増しをして、
家の中を次々と綺麗に直していく父の作業を、葵は傍で見ているのが好きだった。
父は、葵に手伝わすこともしなければ、声をかけることもなかった。
声を持っているのかと疑うほどの寡黙な父。
叱られる時も、言葉はなく、手足が飛んでくるので、
父が帰宅する時間になると、兄弟姉妹の誰かが表通りまで出て、
父の姿を見つけると、皆で一斉に、散らばった自分たちの靴や草履を整えた。
父は本妻の子ではなく、後妻の子で、父の母親は、父を産んですぐ病で亡くなったと、母から聞いた。
父は自分の事を話すことがなかった。
六歳で奉公に出されたと、誰かから聞いたことがある。
その奉公先も大工職人だったらしいが、六歳で大工仕事ができるはずもなく、
父が初めて就いた仕事のことは結局誰も分からなかった。
葵は、好景気が続く西陣織の、機織りの仕事に就いて経験も長く、実家を支える収入もあった。
雄一と一緒に協力しながら、父のように、この長屋を住み易く直して、この新しい大家族を守っていくのだと決心した。
結婚して間もなく、葵は妊娠してしまった。
「年上女房」という言葉が負のイメージを起こさせ、自分が偏見と好奇の目で見られていることも知っていた。
その偏見で、元々結婚を快く思っていなかったと姑は、
妊娠したことを告げた葵を一瞥し、
一番奥の部屋から出てこないよう告げた。
葵の妊娠が分かった時、雄一は職に就いてなかった。
何をしても続かない、三日働いて三カ月遊ぶ、
家族の生活は葵の稼ぎで繋いでいたが、悪阻がひどく、妊娠中毒症状も表れていて、
働く事ができなくなった。
父が揃えてくれた嫁入り道具は、ひとつ、またひとつと、質屋に流れて行った。
八人の生活を支えていたのは、早くに亡くなった、雄一の実父の少額の遺族年金と、
姑の糸繰り賃、十七歳で織屋に見習いにでた妹の収入。
姑の内縁の夫は仕事をしているようだったが、家計の助けにはなっていなかった。
妊娠に加え収入の無い身で、姑や妹からのお小言は、日に日に増し、
働こうとしない雄一との未来に、葵は少しずつ不安を持ち始めた。
まだ子供を産むのは早いのではないか。
骨髄炎の後遺症は、妊娠にも影響が出ていた。
右足と腰に負担がかかり、下半身が鉛のように重い。
体の苦痛と、働けない負い目、回りからの重圧。
中絶しよう。
妊娠した葵に[おめでとう]と声をかける者は、一人もなく、命の始まりを、喜ぶ人は誰もいなかった。
中絶の費用にできる家財道具は、もう鏡台しか残っていない。
これを質に入れてしまったら、父から貰えた想いを全て手放すことになる。
兄に費用をお願いするつもりで、家をでた。
路面電車に乗り込み、座席に腰を下ろした。腰と膝に痛みが走った。
兄に費用を借りるには、この生活の中身も話さなくてはならない。
言えない。
葵は、電車を降り、乗ってきた道のりを歩いて戻った。
やはり、父に話そう。
結婚して初めて実家に帰る理由は、喜ぶべき妊娠の報告であってほしかった。
「初めての子供は、神の子だから、下ろすな。」
父の言葉に、下を向いていた葵は頭をあげた。
殴られる覚悟もしていた。
思いがけない父からの返答に、葵は目も動かせなくなった。
じっと父の目を見たまま、次の言葉を待った。
父は何も言わず、立ち上がって、
「帰りなさい。」
とだけ言った。
父からの「神」という言葉は衝撃だった。
その日、葵は母から、父は信心深く、薄給の中から、寺院に寄付をし、お布施を毎月欠かさずしていることを聞いた。
知らなかった父の一面が、存在をさらに大きくした。
父が望んでくれた子供。産もう。絶対に。
葵はまた、機織りの仕事に復帰した。
妊娠中毒症状の薬を飲み、月に二回、悪阻を抑える注射を受けながら、ふっ切ったように織った。
私が、母のお腹にいた頃の音楽は、
ガシャンガシャンという、鉄で出来た機織りの機械が回る音です。
あなたは聞いたことはありますか?
きっと誰も胎教には良いとは言わないでしょうね。
話す声も聞こえない位の轟音で、決して美しい音色とは言えないけれど、
規則正しく力強く、私への母の想いも、同時に響いていたのだと思います。

 前のページ へ
前のページ へ