枯れない無花果〜閉ざしてしまった篭
蓮 (ren)
『枯れない無花果(いちじく)~閉ざしてしまった篭』。
『手紙的小説』と言えばいいのか?この作品に出逢った時に衝撃が走りました。
荒削りの作品ではありますが、著者の『泥』や『毒』が文字一つ一つの『言の葉』に詰まっています。
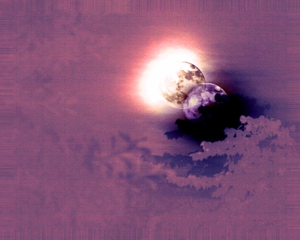
徒 波(アダナミ)
第 7回

保育園の木の門が、境界でした。
「いってくるね、みんなと仲よくね、おむかえまでがんばってね。」
門のところで、母はいつも、そう声をかけてくれますが、
私は無言のまま、行ってしまう母を、目で追いかけました。
皆は、元気良く教室に入っていくけれど、
私だけは、いつまでも門の前から離れませんでした。
門が閉じられると、胸に痛みが走り、孤独が押し寄せ、涙が溢れてきます。
泣き疲れると黙り込みました。
「教室に入りなさい!」
叱られても、すぐに帰ることができるように、
帽子をかぶり、カバンをさげたまま、門の前に立っていました。
私は団体生活が全くできない子供で、皆と一緒に何かをする事を嫌いました。
お昼寝の時間、教室には幾つもの布団が二列に並べられ、
そこへ皆が、一斉に寝転がると、
先生は、一人一人の目の上へ、順番にハンカチを置きにまわります。
この時が、一番嫌いでした。
明かりを遮断する意味があるのでしょうが、
ハンカチを置かれると同時に、皆が寝息を立てる光景が、
奇妙でたまりませんでした。
目隠しをされるということが、なによりも苦痛でした。
この時すでに、不眠症を持っていた私にとって、
眠りたくなくても、横にさせられて、
目隠しで、外部との関わりを断たれる感覚が、とても恐かったのです。
ほとんど毎日、寝返りをうつフリをして、ハンカチを顔から落としました。
でもすぐ見つかって、ハンカチは目の上へ戻されます。
それを何度も繰り返すと注意を受けます。
そこで、頭をちょっぴり傾けて、ハンカチを少し、ずらしてみます。
先生は、直しに来ません。
ハンカチの隙間から教室を眺めます。
皆の書いた絵、オルガン、飾り付け、好きなものを順番に。
少し目を閉じてみます。
閉じた目の中に光の残像が現れ、花のように広がります。
大きくなったり小さくなったり、色が変わったり、
ダンスする光の変化を、楽しみました。
それに飽きると、そっと、教室を抜け出しました。
皆のお昼寝の時間が、先生達の休憩時間だったのでしょう、
先生が教室から居なくなるのを見計らって、
カバンと帽子を持って、運動場に出てブランコに座りました。
まだブランコを漕ぐことはできなかったけれど、
ブランコからは門が正面に見えます。
じっと門を見ていると、今にも母が迎えに来てくれるようで、そわそわしてきます。
でも間もなく先生に見つかってしまい、私は布団の上に戻されます。
カバンと帽子を取り上げられると、癇癪をおこして泣き、
皆のお昼寝の邪魔をして、罰を受けます。
子供達が受ける罰は、いつも園の北奥にある、
会議や、お遊戯会に使用するだけの、大きな部屋に、ひとり入れられます。
この部屋の壁には、天井から床まで、暗幕が掛けられていていました。
窓もすっぽりと覆われて、暗くて静かでした。
ロッカーと少しの荷物が置いてあるだけで、走れるくらいにスッキリと広くて、
秘密の宝物の部屋を、プレゼントして貰ったような気分でした。
ビロード製の暗幕の、手触りを楽しんだり、木の壁の節を眺めました。
部屋の中央に、仰向けに寝ころがって
「あ」と声を出すと、天井に跳ね返って少し響きます。
窓側の端っこに座って、暗幕にくるまりながら、
外の音や、前の道を通る人の気配を観察しました。
皆と居るよりも、私はこの部屋を好みました。
給食の時間も戦いでした。
アルマイトのカップに入った、温かい脱脂粉乳を、
どうしても飲むことができなくて、
膜の張った中味を眺めていました。
教室に立ちこめた給食の匂いと、湿ったような教室の古木の匂い、
子供達の汗の匂い、強烈な脱脂粉乳の匂いとが入り混ざって、
まるで一つの大きな鍋に、これらを全部放り込まれ、
私もその中で、一緒にグツグツと煮立てられているような気分でした。
決心して、めいっぱい口に脱脂粉乳を含むと、
一気に胃に下ろして、すぐコッペパンを口に入れます。
胃の中のものが戻ってこないように、しばらくパンで喉に栓をするのです。
パンは香ばしくて、ほんのり甘くて、優しく口の中で納まってくれます。
そうやって毎日、この時間を乗り越えました。
母が迎えに来るのは、いつも遅い時間でした。
運動場や、門が見渡せる、階段の一番上に腰掛けて、いつも母を待っていました。
お迎えが遅い子供達同士には、不思議な連帯感が生まれてきます。
ある日、上級組のお姉さんが話しかけてくれました。
するとその後ろから、同じ顔をしたお姉さんがもう一人、顔を出しました。
同じお姉さんが二人。私の右手を一人が持って、もう一人が左手を持って、
遊びに誘ってくれたのです。
緊張がすっと抜けて、愉快になりました。
ゆみちゃんと、まさちゃん。
その日のうちに、私はすっかり二人になついてしまいました。
ゆみちゃんは、おとなしくて、ゆっくり話します。
まさちゃんは、早口で、ブランコを大きく高く漕ぐことができました。
まさちゃんの方が、偉そうに見えるのですが、
本当は、おとなしいゆみちゃんの方が、偉いのです。
なにかと指示したり世話をやくのは、ゆみちゃんでした。
運動場の端にあるザクロの木には、朱色をした実がパクっと割れて、枝を下げていました。
ザクロを欲しがった私のために、低いところの一つをとって、
手渡してくれたのは、まさちゃんです。
中の実をとって、食べ方を教えてくれたのは、ゆみちゃんです。
この日から、保育園で過ごす時間が少しだけ楽しみになりました。
朝、保育園の門をくぐると、一目散に上級組みの教室へ行って、
ふたりの横にぴったりと、くっついていました。
ゆみちゃんが、お休みの日は、以前にも増して私は一日中泣いていました。
皆はよく先生にほめられているのに、私は叱られてばかりでした。
どの先生にも心を開かず、泣きました。
毎日こんなで、全く規律に従うことをしない子でした。
ある日、先生達は母を呼びつけ、
「こんな難しい子は、もうここでは預かれません。」
と、退園を迫りました。
ちょうどこの時、続けて父が家に帰らなくなっていた頃で、
仕事、祖母や叔母との緊張関係、母は相当、疲労が重なっていました。
悔しさと悲しみと、たったひとつの支えだった私さえも、
思うように育ってくれない。
私を家に入れ、母は墓地に出かけ、塀に隠れて泣きました。
泣いて顔を上げると、
あの子は何も悪いことはしていない―――
母は、園に向かい、はっきりと退園を拒みました。
そして、たまに帰ってくる父に、母は少しずつ話をして、
長屋を出ることを提案しました。
その時、父が言いました。
「この子が男の子やったらよかったのに。」

 前のページ へ
前のページ へ