枯れない無花果〜閉ざしてしまった篭
蓮 (ren)
『枯れない無花果(いちじく)~閉ざしてしまった篭』。
『手紙的小説』と言えばいいのか?この作品に出逢った時に衝撃が走りました。
荒削りの作品ではありますが、著者の『泥』や『毒』が文字一つ一つの『言の葉』に詰まっています。
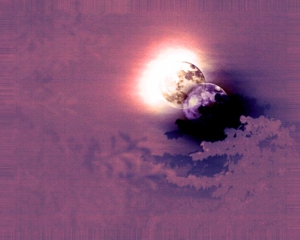
魂 魄 こんばく
第 4回

早朝だったが、助産院のドアは開いていた。
ドアを開けると同時に助産婦が出てきて、
「来た?」
「はい、強い痛みで。」
助産婦は葵の下腹部に触れると、
「まだ下がってきてないから、座って待っていて。表の植木鉢を中に入れてしまうから。台風が来るらしいよ。」
助産婦は手早く植木鉢を待合室の中に入れ、葵を診察室に招き入れた。
「降りてきてないね。ちょっと苦労するかな。
逆子ではないけど、初産だからね。時間かかるね。
今日は出てこないと思うけど、どうしようか、
台風も来るようだから、今日から入院する?」
またあの道のりを、帰りたくない。
しかし、入院するとなると、費用が掛ってしまう。
「有難うございます。今日産まれないなら、帰ります。」
台風が近づいている気配はなかった。
家に着くと、暑さと痛みで吐いた。
何も食べてなくても吐気が治まらない。
這うように奥の部屋へ入り、畳んである布団に倒れ込んだ。
腰湯をする気力すらなかった。誰かに背中を、さすって欲しかった。
意識が霞む。ウトウトと、眠りかけたらまた陣痛がくる。
台風が来るらしいが、姑が干していった洗濯物が、外に出たままだ。
一瞬、気になったが、どうでもよくなった。
食事の支度も、雄一の食べる分は、昨日の支度したものが、そのまま残っている。
助産婦は、苦労するかもと言っていた。難産になるのか。
明日もう一度行ったら、入院しようと決めて、少し眠った。
気がつくと、陽は暮れ、部屋は暗く、吐気はおさまっていた。
表の部屋で姑や妹たちの話す声が聞こえた。
ゆっくり起き上がった。
電気をつけても、誰も様子を見には来ないだろう。
そのままそっと便所へ行き、台所の水道でコップ1杯の水を入れ、
一気に飲み干してから、また奥の部屋へ入った。
陣痛が始まって三日目も、同じだった。
子宮口が緩んでないと告げられた。
昨日も雄一は帰宅していない。入院費用の相談もできていない。
辛そうだから此処に居なさいと促す、助産婦に、
「明日また来ます。」
頭を下げて外に出た。
寺の中を歩きながら、お腹に手を当てて、
「出て来たくないのですか、赤ちゃん。
何があってもお母さんが守りますよ。出ておいで。出ておいで。」
あのステレオを質にいれようか。
あれを手放したら、終わりですね。
玄関が開いていた。表の部屋で、
近所に住む雄一の将棋仲間の声と、雄一の姿があった。
「これ、もらったから、茹でて。」
新聞紙に包まれた、茎の付いた枝豆を葵に渡し、
将棋盤を準備して、いそいそと外に出て行った。
路地の隙間の窪地に長椅子を置いて、雄一はいつもそこで仲間と将棋を打つ。
葵は、放置されたままの雄一の夕餉をゴミ箱に捨て、鍋を持って井戸の水を汲み、
枝豆を洗い、鍋に火をかけた。
くつくつと温度を上げる鍋。
「こんな世界に、出てきたくないか・・・。」
茹であがった枝豆を笊で水を切り、塩をふって皿に盛り、
ひとつふたつ、口に入れた。
私が食べないと、赤ちゃんも食べられない。
もうひとつ、もうひとつ、何とか、飲み込めた分だけ。
のみ込んだ後、枝豆の皿をそのままにして、奥の部屋へ籠った。
将棋を終えても、雄一は友人を部屋に招き入れ、
帰宅した姑が食事を作り、妹たちと夕食を食べ、
酒が入って上機嫌のまま、また友人と出かけていった。
費用の話は出来なかった。
四日目は、助産院へ向かわなかった。姑が家に居たので、費用の相談をしたかった。
この家は、近所の人間が頻繁に出入りする。
その日も、朝からにぎやかな人たちが、世間話をしに姑を占領していた。
痛みが治まる度に、奥の部屋から様子を窺いに表を覗いてみたが、声をかけられずにいた。昼を過ぎると、激しい痛みが襲い、頻繁に来るようになった。
これ以上待つと、歩けなくなる。今のうちに向かおう。
玄関を出て、路地を曲がるとき、振り返ると、
雄一はまた路地の窪みで、仲間達と、将棋を打っていた。
台風接近の、生ぬるい湿気を帯びた風が吹き始めた中を、ひとり助産院へ向かった。
「今日は出て来そうだね。」
この言葉を待っていた。
「分娩室に入るには、まだ早いから、待機室で子宮口が開くのを待つからね。」
痛みの波に耐えながら、畳の待機室で、陽が落ちるまでずっと、
窓の外に舞う木の葉を眺めていた。
外が暗くなって、葉の色も解らなくなった頃、
やっと分娩室に移動し、出産の準備に入った。
体力のなくなった体に、今までとは違う激痛が押し寄せ、何度も気が遠くなり、
次第に眠気が襲い始めた。
眠りたい。
頬を叩かれて、目が覚めた。
「眠るのは産んでから。」
いつの間に用意してくれたのか、助産婦は冷えた手拭いで、何度も顔をふいてくれた。
それでも、自然に目が閉じていく。
様子がおかしいと察した助産婦は、
「座れる?座って産みましょう」
と、しゃがみこむ姿勢をとらせた。
もう起きあがる気力も体力も無かったが、両足を踏ん張り、全身に力を込めた。
それから間もなく、大きな波のような陣痛がきて、
助産婦の声に合わせて目を開き、大きく息を吸い込み、最後の力を絞り出した瞬間。
私は母から分かれました。
母は、その場に倒れ込み意識が薄れながら助産婦からの、
「おめでとうさん、女の子ですよ」
と言う声を聞くのですが、赤ちゃんの泣き声が聞こえません。
私は泣かず、呼吸もせず、全身紫色で仮死状態でした。
すぐさま助産婦は、私の両足首を持ち、逆さにして、何度もお尻を叩きました。
ビタンビタンという音。続いたのが数秒ほどだったのか、数分だったのか、
もっと長かったのか、定かではないのですが、母にはとても長く感じたそうです。
私は[何かに気づくような声]を、ひとつ出し、それが泣き声に変わってからは、
部屋中、響き渡るような、大きな大きな、力強い声で泣いたそうです。
私が生まれて、最初に人から受けたことは、
母の抱擁でも助産婦の抱擁でもなく、温かい産湯でもなく、
逆さまにされてお尻をぶたれることでした。
笑ってしまうでしょ?
それを母から聞いたとき、私は思わず笑ってしまいました。
まるで、これからの私の人生を物語っているようで。
人生は甘くない、生きることは痛みを伴うこと、
私の未来は抱擁ではなく痛みを克服すること。
きっと、それを知っていたから、
私は四日間も、母のお腹から出てくるのを嫌がったのでしょう。
だけど、お尻をぶったその助産婦が、
唯一、私の命を「おめでとう」と言ってくれた人です。

 前のページ へ
前のページ へ